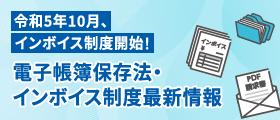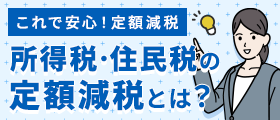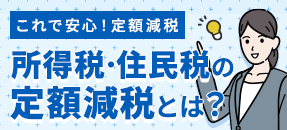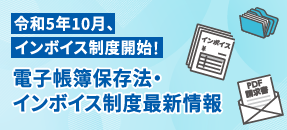創業55年。経営をお助けするのが、税理士の役目です。
当事務所は『健全な会計に健全な精神宿る』をモットーに、経営コーチの税理士として大阪を中心に多くの顧問先様のパートナーとして歩んでまいりました。創業55年の実績と人材でサポートします。
その中で、黒字申告のお客様が今でも90%以上であることがその信頼と実績の証です。
私たちのノウハウをあなたの会社にも導入してみませんか?
誰に相談していいかわからない…そのお悩み、税理士にご相談下さい。
経営を行う上で、一人で悩まれている方は多数いらっしゃいます。その様なお客様に対し、一人でも多く解決するため、私たちは一人一人に親身になり迅速な対応を心掛けています。これまでに数々の実績を生み出してきた私たちにお悩みをお聞かせください。
当事務所は大阪を中心とした中小企業を元気にします!!